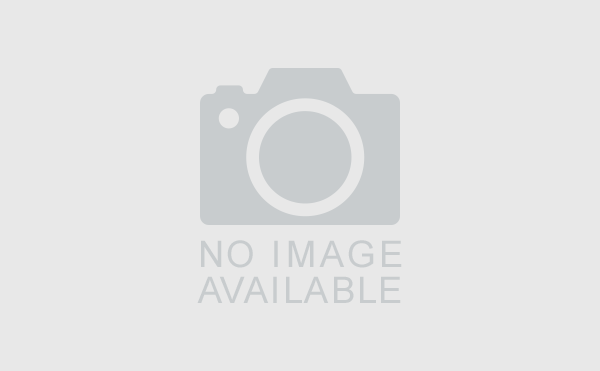■建設業許可申請での確定申告書のポイント!
今回は、特に個人事業主時代の建設業での経営経験を証明する場合に
特に大切なポイントについて解説。
いわゆる建設業での経営経験が5年とか7年とかという話です。
建設業許可申請を行う場合には許可要件をクリアする必要があります。
そのなかで、「経営業務管理責任者」という重要な要件があります。
個人事業主として建設業を5年や7年以上していることや、
法人では取締役などの地位で経営に携わったことなどが必要となる話。
その中で、個人事業主としての場合についてココでは考えます。
個人事業主として建設業を営んでいたという証明で一番大切なのが、
「確定申告書」の存在!
確定申告を個人事業主は毎年するわけですが、
あなたはどういうかたちでされていますか?
ご自身で税務署に書類を持っていき控えに受理印を押してもらうパターンですか?
それとも、お世話になる税理士さんが申告してくれるパターンですか?
その場合は、電子申告されているのでしょうか?
または、ご自身で電子申告されていますか?
現在は、このどれかのケースしかないと思いますがどちらでされていますか?
確定申告だけを考えるとどの形であれそんなに気にすることもないかもしれません。
しかし、
建設業許可申請を行う場合はちゃんとわかっておく必要があるポイントがあります。
それが、「受理印」
■受理印は建設業許可申請では重要なポイント!
ご自身で確定申告を税務署で行った場合、
控えに「いつ受付ました。」
という受理印を押してくれます。
これが単純なことですが、とても大切なポイント!
仮りにですが、この「受理印がない」ことを想像してください。
控えがあったとしても、「本当に確定申告した?」
と疑われても仕方ないと思いませんか?
もうわかりましたか?
そうです。
この確定申告書の控えがあり、受理印がキッチリあればこの期間は
個人事業主として商売をしていましたね。
と見てくれるということなんですね。
つまり、建設業許可申請では、経営者としてこの期間商売をされていましたね。
という証明になるのです。
一方、ご自身や税理士さんが電子申告で確定申告をした場合。
この場合も重要なポイントがあります!
それが、控えはもちろんですが、
「送信されたデータを受け付けました」
などが書かれている用紙を手元に確定申告と一緒に(セットで)置いておく。
この場合も控えだけあっても本当に申告した控えかどうかはわからない。
だから、「受け付けました。」という先方が発行する書面が必要となるんですね。
つまりこれは、受理印と同じ意味のものといえますよね。
この受理印をキーワードとして確定申告書が必要となります。
このポイントは大切なところですね。
これで建設業許可申請の一歩を踏み出せますね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
宮っこ行政書士 山中英資

お問い合わせ
建設業許可申請に関するお申し込みお問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。
お客様が疑問に思っておられることご不明な内容も、メールフォームもしくはお電話でご連絡頂けましたら速やかにご回答させて頂きますので、当事務所までお気軽にご連絡ください。